お疲れ様です、ichiです。
今のご時世、車にETCを取り付けるのは常識になってきています。
高速道路の利用をスムーズにするには、ETCは必須。
しかし、ETCにもさまざまな種類があることはご存知ですか?
性能や電源の確保、セキュリティや機能の違いなど、ETC車載器により異なってきます。
今回は、そんな機能や性能の違いや選ぶ際のポイントを紹介していきます。
これからETCを購入しようと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
べつの記事で、ETC車載器の取り付けについても解説しています。
よければこちらもご覧ください。

YouTubeでも配信しているので、動画で観たい方はこちらをどうぞ。
ETCの選び方

ETC車載器といっても、種類や機能は多種多様。
ETC車載器を選ぶ際のポイントは、利用シーンや目的に応じて適切な機能を選ぶことが重要です。
まずはETC車載器の選び方を詳しく紹介していきます。
ETC車載器の種類を確認する

ETC車載器には、大きく分けて2種類があります。
ETC1.0
高速道路や有料道路の料金支払い専用。
シンプルで価格が比較的安い。
- 主に料金収受の自動化を目的としたシステム。
- 車載器と料金所のアンテナが通信し、通行料金を支払う仕組み。
- 通信は狭域(約30m)で行われ、情報量が少ない。
- 提供されるサービス
-
料金の自動収受のみ。
- 通信方式
-
DSRC(狭域通信)のみを使用。
通信可能範囲が料金所付近に限定。 - 導入の利便性
-
導入費用が比較的安価で、単純な料金収受が目的の人に適している。
- 将来性
-
基本機能は維持されるが、サービス拡張の予定は少ない。
ETC2.0
高速道路の高度化サービス(渋滞情報、災害時の情報提供、ルート案内など)に対応。
ドライブを快適にしたい場合におすすめ。
- 料金収受に加え、高度道路交通システム(ITS)の一部として、交通情報の提供や渋滞緩和を目的とする。
- 広域通信(約1000m)が可能で、双方向通信により大量のデータをやり取りできる。
- 高精度のGPS情報を活用し、位置情報をもとにサービスを提供。
- 提供されるサービス
-
料金収受に加えて以下のサービスが利用可能
- ルート別料金計算:走行ルートごとに細かく料金を計算(経路特定型料金)。
- 渋滞回避支援:渋滞や事故情報をリアルタイムで提供し、最適なルートを案内。
- 災害時の支援:災害時に迂回路や通行可能なルートを提供。
- 駐車場案内:サービスエリアやパーキングエリアの空き情報を提供。
- 通信方式
-
DSRCに加えてITSスポット通信を活用。
高速道路の広範囲で通信可能。 - 導入の利便性
-
導入費用はやや高いが、多機能性と利便性が向上。
特に長距離ドライバーや物流業界で有用。 - 将来性
-
高度な交通システムの一環として、さらなるサービス拡充が期待される。
「ETC1.0」と「ETC2.0」の違い
双方の違いを簡単にまとめると、こんな感じ。
日常的な利用で十分ならETC1.0、情報提供や高度なサービスが必要ならETC2.0を選ぶとOKです。
音声案内機能の有無

音声案内があると、料金支払いやエラー発生時に分かりやすいです。
車内の音響や使いやすさを考慮し、音声案内の音質や、音量調整が可能な機種を選ぶと良いでしょう。
これまで音声案内のないETC車載器を使ったことはありませんが、音声案内のないETC車載器もあるかもしれないので注意してください。
カード挿入状況の確認機能

カードの挿し忘れを防ぐため、電源ON時に「カード挿入済み」や「カード未挿入」を案内する機能があると安心です。
ETC車載器で怖いのは、やはり抜き忘れたことによりETCカードを窃盗されてしまうこと。
ほとんどのETC車載器にこの機能はあると思いますが、購入時には確認してみてください。
アンテナのタイプ

アンテナも2種類のタイプがあります。
- 一体型
-
車載器本体とアンテナが一体化しており、配線が少なくスッキリ設置できる。
設置が簡単。 - 分離型
-
アンテナをダッシュボードやフロントガラスに設置するタイプ。
感度が良く、車内の美観を損ねにくい。
選ぶポイントとしては、車内のデザインや取り付けスペースを考慮して選ぶこと。
私が購入したのは、分離型タイプです。
電源の接続方法

ETC車載器にも、電源が必要になります。
- シガーソケットタイプ
-
手軽に取り付け可能。
シガーソケットを占有される上に、見た目も悪い。 - 直結配線タイプ
-
車両の電源に直接接続するため、すっきり設置可能。
ただし取り付けには専門知識が必要。
シガーソケットから電源を取るとなると配線が剥き出しになるので、おすすめは直結配線タイプ。
基本的にヒューズボックスから電源を取りますが簡単に自分でも出来るので、電気系が苦手な方もチャレンジしてみてはいかがでしょう?
セキュリティ機能

高速道路でカードが抜かれることを防ぐ「カードロック機能」や、盗難防止のための暗証番号設定機能があると安心。
取り付けやセットアップ

専門業者による取り付けが必要な場合が多いので、取り付け費用も予算に入れる必要があります。
しかし、ナビ・オーディオやスピーカーに比べて、ETC車載器の取り付けは簡単なので、DIYにチャレンジしてみるのもいいかも。
ただし、セットアップに関してはお店でしか出来ないので要注意。
ETCカードとのセットアップ作業が必要なので、購入時にセットアップ料金も確認しておいてください。
セットアップについては、購入時にセットアップされた状態で手に入れるか、購入後にディーラーやカーショップで依頼することになります。
将来の拡張性

将来的にETC2.0や高度なサービスを利用する可能性があるなら、最初から「ETC2.0」対応の車載器を選ぶと無駄がないでしょう。
- ETC1.0
-
基本機能は維持されるがサービス拡張の予定は少ない。
- ETC2.0
-
高度な交通システムの一環として、さらなるサービス拡充が期待される。
ETC1.0は「料金収受専用」、ETC2.0は「料金収受+交通情報サービス」と考えるとわかりやすいです。
渋滞回避やルート案内など、より快適なドライブを求める場合はETC2.0がおすすめです。
まとめ

ETC車載器を選ぶ際は、使用する車やライフスタイルに合わせて、機能やデザイン、価格をしっかり比較検討することが大切です。
特に、取り付けの簡単さや利用頻度に応じた性能、セットアップに必要な費用を考慮することで、より満足度の高い選択ができるでしょう。
自分に合ったETC車載器を見つけることで、ドライブがさらに快適でスムーズなものになるはずです。
これからETCを購入しようと思っている方の、少しでも参考になれば幸いです。
それでは皆さま、ご安全に。
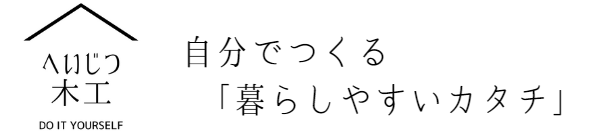

コメント